


このような悩みを解決する記事です。

ぼくは23歳の時にお金にたいして漠然とした不安を感じていました。
このままではダメだと思い、24歳の時にFP技能士2級を取得。
今後もみなさんにお金に対する有益な情報を共有できたらと思っています。
プロフィールは下記のとおり。
プロフィール
- 24歳でFP技能士2級の資格を取得
- 旧NISA、新NISAでインデックス投資(2022年~継続中 +15万円の利益)
- 毎年ふるさと納税で3~5の自治体に寄付して節税
- 家族の家計管理、資産運用、保険の見直し
- 現在もお金に関する知識をアップデートしながら情報発信中
がんばって稼いだ給料がたくさん税金でひかれてるとショックですよね…
近年では物価も高くなり家計が苦しくなっている家庭も多いのではないでしょうか?
「節税」と聞くと自営業を思い浮かべる方がおおいかと思いますが、結論。サラリーマンでもできる節税方法はあります。
今日はFPのぼくがみなさんにおすすめする節税方法を4つ紹介します。
かなりお得な節税方法もあるんですが、サラリーマンでも節税している人は意外に少ないです。
ですが、知っていないと生涯で大損レベルの節税方法があるのも事実。
節税方法を知っているかどうかで生涯にかなりのお金の差が生まれるので、ぜひ自分にあった節税方法を見つけてくださいね。
この記事を読むメリットは以下のとおり。
- あなたにあった節税方法が見つかる
- それぞれの節税方法のしくみがわかる
- 節税することで今よりあなたの家計が楽になる
目次
サラリーマンができるおすすめ節税方法4選
ぼくがおすすめするサラリーマンにできる節税方法は下記の4つです。
以下の4つはどれもむずかしくない節税方法なのでおさえておきましょう!
- ふるさと納税
- 医療費控除
- iDeCo
- 新NISA
上記4つがサラリーマンにできるおすすめの節税方法です。
とくにふるさと納税はかんたんにできて、年間数万円単位でお得な制度なのでぜひ活用してくださいね。
では、それぞれの節税方法を解説していきます。
【ふるさと納税】 おすすめ度:☆5 難易度:かんたん

サラリーマンでお得に節税するなら、ふるさと納税がおすすめです!
みなさんも一度は「ふるさと納税」という言葉を聞いたことあるのではないでしょうか?
ふるさと納税をかんたんに説明すると、「毎月に支払っている住民税を他の地域へ先払いして、自己負担2000円で返礼品をもらおう」という制度です。
普段は毎月のお給料から住民税が差し引かれていると思いますが、ふるさと納税することによって来年の住民税が減額されます。
| 住民税 | 返礼品 | |
| ふるさと納税していない場合 | 通常通り毎月支払い | なし |
| ふるさと納税した場合 | ふるさと納税した額に応じて減額 | あり |


ふるさと納税することによって地域の特産品で食費が浮いたり、ほしかった家電が手に入るのでただ住民税をおさめているのはもったいないですね。
近年ではワンストップ特例制度により返礼品と一緒にワンストップ特例制度の用紙が入っており、より簡単にふるさと納税ができるようになりました。
※もし確定申告するならワンストップ特例制度は利用できません。


それぞれの年収や家族構成に応じて毎年ふるさと納税できる上限額が決まっています。
上限額を超えるとただ寄付をしただけになり損してしまう可能性もあるので注意です。
【例】年収500万円独身だと、年間の上限額が58,000円
ふるさと納税サイト「さとふる」にて数分であなたのふるさと納税上限額がわかるので、ぜひシミュレーションしてみてくださいね。


ふるさと納税の手順は以下のとおり。
- 普段ネットショッピングで買い物をするのと同じように寄付する。
- 寄付した地域の返礼品と「ワンストップ特例制度」の用紙が届く。
- ワンストップ特例の用紙を記入してポストへ投函orインターネットでマイナンバーカードを使いワンストップ特例申請
- 来年の住民税が減額される

ふるさと納税のポイントは以下のとおり。
- ふるさと納税は他の地域に住民税を先払いして自己負担2000円で返礼品がもらえるお得な制度。
- インターネットでネットショッピング感覚でふるさと納税ができる。
- ワンストップ特例を使用するとよりかんたんに申請できる。 ※確定申告するなら使用不可
- ふるさと納税では地域の特産品や日用品が返礼品としてもらえるから生活費の節約になる。
【医療費控除】 おすすめ度:☆4 難易度:ふつう

サラリーマンができる節税方法として医療費控除がおすすめです。
医療費控除は確定申告する必要があるので、聞いたことある人は少ないかもしれません。
医療費控除とは年間で医療費がたくさんかかってしまった人が利用できる節税方法です。
かんたんに説明すると、年間で支払った医療費の総額が10万円を超えると支払った額に応じて確定申告することにより所得控除してくれる制度になります。
医療費控除は本人の医療費のみならず、生計を共にする配偶者(扶養でなくてもよい)、子どもの医療費も含まれます。
所得控除された後の年収に税率をかけることによって支払う税金が安くなり節税になるのです。
医療費控除によって節税ができるわかりやすい例は下記のとおり。
| 年収 | 医療費控除により所得控除した額 | 支払う税金 | |
| 医療費控除をしていない場合 | 500万円 | 0円 | 500万円×税率 |
| 医療費控除をした場合 | 500万円 | 200万円 | 300万円×税率 |

ぼくも実際に治療目的の歯の矯正治療した際は、100万円ほど所得控除になりました。

ただし、医療費であっても対象になる項目と対象にならない項目があるので注意です。
医療費控除の対象にならない医療費は以下のとおり。
医療費控除の対象にならない医療費
- 美容目的の治療
- 健康診断、人間ドックに費用 ※重大な病気がみつかりそのまま治療に移行する場合は医療費控除対象
- インフルエンザ等の予防接種費用
- 入院した際、個室を選択した場合の差額ベッド代
医療費がかかった際は医療費控除の対象であるか対象でないかはしっかり確認して領収証を保管しておきましょう。
医療費控除のポイントは以下のとおり。
- 年間の医療費の総額が10万円超えると確定申告することにより所得控除ができる。
- 所得控除されることによって税金が安くなり節税になる。
- 医療費は本人のみならず生計を共にする配偶者(扶養でなくてもよい)、子どもの医療費も含めてよい。
- 美容目的の医療費は医療費控除の対象外であり、事前に確認しておくことが必要。
【iDeCo】 おすすめ度:☆3 難易度:むずかしい

サラリーマンが資産形成するうえでお得な節税制度のひとつとしてiDeCoがおすすめです。
近年、老後2000万円問題が世間で騒がれており老後のお金に不安に感じることありますよね。
iDeCoはそんな老後2000万円問題や資産形成にたいしてとても有効な節税制度です。
iDeCoとはかんたんに説明すると、原則65歳まで引き出せないが、投資により資産形成して掛け金が所得控除される制度です。
月ごとにiDeCoで投資できる額の上限額も決まっており、企業年金に加入しているサラリーマンだと月の上限20,000円。企業年金に加入していないサラリーマンだと月の上限23,000円になります。
iDeCoで購入できる投資商品は国が認めた投資対象のみになっているので、あやしい投資やぼったくりな投資対象がないのも安心して資産形成できるおすすめのポイントのひとつ。
なかでも、優良のインデックスファンドに投資しておくと低く見積もっても年利4,0%~7,0%の成果を出すといわれており、ただ銀行に預けて貯金するよりも断然お得だといえます。
※銀行金利だと高くても0,20%~0,30%だといわれています。


本来投資とは長期でコツコツと複利の力を利用して資産を大きくしていくものであり、短期間で投資商品のトレードをするのはかなりギャンブルに近い状態だといえる。
だから投資をするうえでは強制的に引き出せない状態にしておくのがベストなんだ。
投資商品の価値が下落し焦って売却しちゃうと長期投資の強みを活かせないからね。

歴史的偉人であるアインシュタインも「複利は人類による最大の発明だ」と名言をのこしたくらいですからね。
iDeCoでしっかり複利の力を利用しながら長期で節税して資産形成していきましょう!
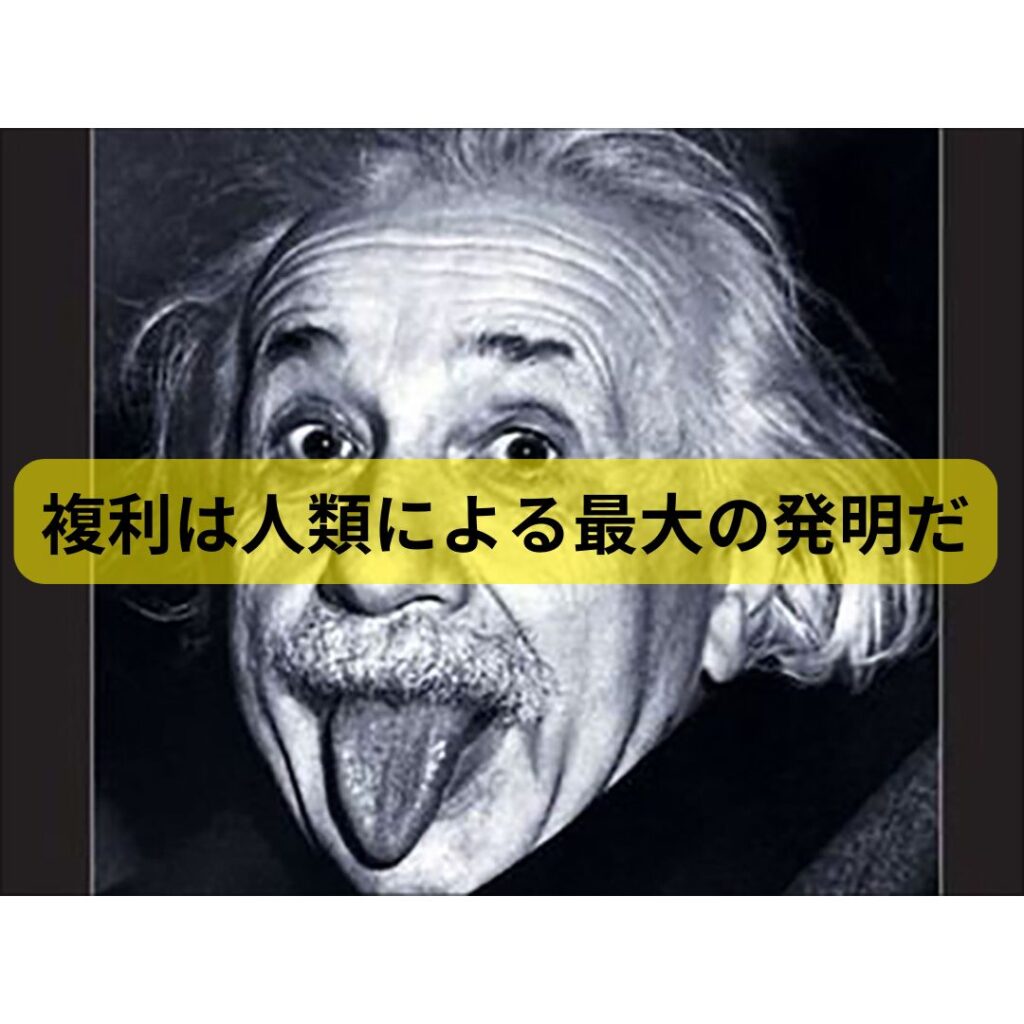
iDeCoのポイントは以下のとおり。
- 株式投資で資産形成しながら投資した額が所得控除できる
- iDeCoでする投資対象はすべて国が厳選した投資対象であるため安心して資産形成ができる。
- 原則65歳まで引き出せない。※投資初心者にとっては引き出せないことが強みになる
- 月の掛け金上限は企業年金加入していると20,000円。企業年金に加入していないと23,000円。
- 今まで投資をしたことないひとには難易度高め。
【新NISA】 おすすめ度:☆3 難易度:むずかしい

サラリーマンが資産形成するうえでお得な節税制度のひとつとして新NISAがおすすめです。
新NISAとはかんたんに説明すると、本来投資によって得た収益は20%の税金がかかるが、新NISA口座で投資により発生した収益には税金がかからないという制度です。
新NISAを始めることによって近年の物価上昇や老後2000万円問題の対策ができます。
新NISAは先ほど紹介したiDeCoと違って、引き出しするにあたっての年齢制限がなく資産の流動性が高いのが大きなポイントです。
株式投資の強みは長期にわたり時間をかけることなので、iDeCoと比較すると流動性の高い新NISAは難易度がすこし高いといえます。
しかし、iDeCoと比較して投資できる上限額が最大1800万円とかなり大きいのでぜひ有効活用したい節税制度です。
新NISAのルールをまとめると以下のとおり。
| 非課税期間 | 恒久(期限無し) |
| 生涯非課税限度額 | 1800万円 |
| 積み立て投資枠 | 年間120万円 |
| 成長投資枠 | 年間240万円 |
| 引き出し制限 | 制限無し |

お得な制度とわかっていても投資で損するのが怖くてなかなか手がだせないよ。
でも、お金の勉強すると投資しないほうが逆に怖いということに気がついたんだ。
考え方としては、「現金のみで資産を保有する=日本円に全額投資している」と同じこと。
お金の価値というのは物価上昇によって年々下がっていくものなんだ。
昔の1万円と現在の1万円の価値は違うでしょ?
年々物価が上昇して去年は1万円で購入ができていた商品が来年には1万1千円必要になるなんてことはよくあるんだ…
だけど、株式に投資しておくと経済が発展するとともに増えてくれるから資産もどんどん増えて物価上昇に対応できる!


ちなみに、月1万円を年利7%で40年間積み立てると以下のとおりになります。


金融庁の積立シミュレーターから引用
元本が480万円なのにたいして運用収益が2145万円。なんと40年間優良のインデックス投信に投資すると合計2625万円になるのです。
年利7%は過去の実績からみても低めに見積もった額ですので、決して高すぎる年利設定ではないといえるでしょう。
若い人は来月からでも新NISA制度を利用して老後や将来の備えを!
新NISAのポイントは以下のとおり。
- 本来投資で得た収益は20%の税金がかかるが、NISA口座なら収益すべてが非課税になる。
- 非課税限度額は元本にたいしてひとり1800万円
- iDeCoと違ってNISA口座からはいつでも引き出せる。
- 新NISAで複利の力を利用することで老後や将来の備えができる。
- 新NISAで毎月1万円を年利7%で40年間運用すると、将来2625万円になる。※購入した銘柄によって結果は異なります。
お金を貯めるなら家計簿から。マネーフォワードMEがおすすめ

みなさんは毎月何にどれだけお金を使っているか把握していますか?
節税制度で自由に使えるお金が増えたとしても支出を把握できずお金を貯金できなければもったいないですよね。
結論、お金を貯めるとき一番有効なのは家計簿をつけることです。
なぜなら、家計簿をつけないと気がつかない間に支出が増えていたり、家計を改善する時にどこから改善していけばよいのかわからなくなってしまうからです。
ぼくも実際にむかしは家計簿をつけていなかったのですが、お金をあまり貯められませんでした。
家計簿をつけだしてから資産形成のスピードも圧倒的に早くなりました。
でも、家計簿アプリは多すぎてどれをつかえばよいかわかりませんよね。
お金を貯めて資産形成するならマネーフォワードMEがおすすめです!
マネーフォワードMEをお勧めする理由は以下の3つ。
- クレジットカードや銀行と連携するだけで自動で家計簿を帳簿してくれる。
- 手動入力はもちろん、レシートの撮影で自動入力も可能。
- 無料で4口座まで連携できて、資産の把握もしやすい。
今までお金にたいして様々な相談を受けてきましたが、お金に困っている人はほとんどの人が自分の日々の家計を把握していないことが多いと感じます。
お金が貯められない人は支出にたいしての感覚と実際に使用している金額の認識にズレがあることが多いです。
あなたもお金にたいしての不安を無くすためにまずは家計簿からつけてみませんか?
まとめ
結論、サラリーマンでも節税は複数あり節税によって家計を楽にすることは可能です。
なかでもサラリーマンができるおすすめの節税方法は以下の4つ。
- ふるさと納税
- 医療費控除
- iDeCo
- 新NISA
どれもサラリーマンとして生きていくうえでお得な節税制度ですが、なかでもおすすめの節税方法はふるさと納税でした。
節税等でコツコツとした努力が10年後20年後に大きな差をひらいていきます。
みなさんも今後ぼくと一緒にお金に困らない生活ができるようお得な節税制度を利用していきましょうね。